不動産の購入や投資、あるいは生活拠点の移転を考える際、「その土地にどんな災害リスクがあるのか」は非常に重要な判断材料です。日本は自然災害の多い国であり、地震・洪水・土砂災害は特に注意すべきリスクです。本記事では、初心者でもできる災害リスク調査の基本的な方法と、公的な情報源を活用した具体的な調査手順について詳しく解説します。
1. 災害リスク調査の重要性とは?
なぜ災害リスクを調べるのか?
不動産は一度購入すれば簡単には移動できません。災害リスクを事前に調査せず購入してしまうと、後で「地震で液状化した」「台風で浸水した」「土砂崩れで通行止めが起きた」などの被害に巻き込まれる恐れがあります。また、災害リスクが高いエリアでは将来的な資産価値の低下や売却困難といった問題も生じる可能性があります。
2. 災害リスク調査の基本ステップ
災害リスクを調査するには、次のような基本的な手順を踏むことが大切です。
- 該当エリアの自然災害履歴の確認
- ハザードマップの参照
- 自治体の防災情報の確認
- 地形・地質・土地履歴の調査
- 現地での確認と聞き取り調査
それぞれの手順について、具体的に見ていきましょう。
3. 地震リスクの調査方法
活断層と震度予測
まず地震リスクの確認において重要なのは、「活断層の有無」と「過去の震度履歴」です。
【チェックポイント】
- 国土地理院の活断層図
地域の近くに活断層があるか確認します。 - 地震ハザードステーション(J-SHIS)
地震動予測地図や最大震度の予測を視覚的に確認できます。 - 地盤の強度(表層地盤増幅率)
地震の揺れが増幅されやすい地盤かどうかを確認。
【参考サイト】
- 地震ハザードステーション(J-SHIS):https://www.j-shis.bosai.go.jp/
- 国土地理院 地理院地図:https://maps.gsi.go.jp/
液状化のリスク
海沿いや埋立地では、液状化現象のリスクもチェックが必要です。地盤が弱く、地震時に地面が「液体」のようになってしまう現象で、建物の傾きや沈下の原因となります。
【液状化の調査方法】
- 各自治体の液状化予測マップを確認。
- 過去の液状化被害の記録を見る。
- 地盤調査報告書(売主が保有している場合)も有用。
4. 洪水・内水氾濫リスクの調査方法
ハザードマップの確認
国土交通省が提供する「重ねるハザードマップ」では、洪水・高潮・内水氾濫などのリスクをまとめて確認できます。
【調査項目】
- 想定浸水深:浸水した場合にどの程度の水深になるか
- 浸水継続時間:水が引くまでどのくらい時間がかかるか
- 避難場所と避難経路の確認
【参考サイト】
- 重ねるハザードマップ:https://disaportal.gsi.go.jp/
内水氾濫とは?
内水氾濫は、下水道や排水施設の容量を超えた雨水が住宅地にあふれ出る現象です。都市部の低地や排水の悪いエリアでは特に注意が必要です。
【対策】
- 地盤の高さを確認(標高が低い場所は要注意)
- 周辺に調整池(雨水貯留施設)があるかを確認
5. 土砂災害リスクの調査方法
土砂災害警戒区域とは?
大雨や地震によって、がけ崩れや地滑りが発生する可能性があるエリアは、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」および「特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されています。
【調査手順】
- 都道府県が提供する「土砂災害情報マップ」を参照
- 住宅の背後に急傾斜地がないかを確認
- 崩壊の危険がある山林や谷の存在を確認
【参考サイト】
- 都道府県の土砂災害マップ(例:大分県:https://www.bousai-oita.jp/)
6. 地形・土地の成り立ちを調べる
地形図・古地図の活用
自然災害は「地形」によって影響を大きく受けます。以下のような点に注目しましょう。
【調査ポイント】
- かつて河川・沼地だった場所(旧河道など)は水害リスクが高い
- 谷地・崖下・盛土造成地は土砂災害や地盤沈下のリスクがある
- 「台地」「段丘」「扇状地」などの地形ごとに災害傾向が異なる
【参考サイト】
- 地理院地図(標高図、陰影起伏図):https://maps.gsi.go.jp/
7. 自治体の公開資料を確認する
各市町村では、防災マップや過去の災害履歴、地域計画などを公開しています。市役所・町役場の建設課や防災担当部署に問い合わせれば、詳細な資料が手に入ることもあります。
【調査するもの】
- 地域防災計画
- 土地利用計画図(用途地域、開発履歴)
- 災害記録集(新聞記事や被害写真)
8. 現地調査で見るべきポイント
最後に、現地を実際に歩いて確認することも非常に重要です。
【現地で確認すること】
- 道路や敷地の高低差、排水状況
- 周辺住宅の基礎の高さや擁壁の有無
- 過去に浸水・土砂災害があったか、近隣住民への聞き取り
【注意すべきサイン】
- 側溝やマンホールの泥痕
- 家の土台部分にひび割れや傾き
- がけや法面にブルーシートがかかっている(応急措置の痕)
9. まとめ:災害リスクを「見える化」する力を持とう
災害リスク調査は、専門家でなくてもある程度のことは自分で行えます。むしろ、自らの目で地形を見て、地図を読み、地域の歴史を知ることが、納得できる物件選びへの第一歩となります。
【チェックリスト】
- ハザードマップを確認したか
- 地震・洪水・土砂災害リスクを個別に調べたか
- 地形や旧地図から土地の成り立ちを理解したか
- 現地を歩き、住民からの声を聞いたか
一見、安全そうに見える土地でも、過去には災害の被害に遭っていたかもしれません。逆に「災害リスクあり」とされている地域でも、対策が進んでおり、リスクが低減されている場合もあります。
正しい情報と調査手法を持ち、自ら判断できる目を養いましょう。それが、安全・安心な住まい選び、そして災害に強い地域づくりにつながります。

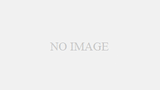
コメント