~不動産調査の第一歩、でも「万能」ではない~
「この土地って誰のもの?」「担保に入ってるの?」「昔からの持ち主?」
こうした疑問に答える第一の資料が**登記簿謄本(登記事項証明書)**です。
不動産取引・相続・担保設定・裁判など、幅広い場面で「登記の中身」は必要になります。
ただし、登記簿を見ればすべてが分かるわけではありません。
不動産初心者の方にとっては、見慣れない用語や構成に戸惑うことも多いでしょう。
この記事では、
- 登記簿謄本の基本構成
- 実際にわかること・わからないこと
- 取得方法と読み方のコツ
- 注意すべき落とし穴
などを、実例を交えて解説していきます。
第1章:登記簿謄本とは?基本構造を知る
登記簿とは?
登記簿とは、不動産(土地・建物)の「公的な身分証明書」のようなものです。
国が管理する「不動産登記制度」に基づき、
- 誰が所有者か
- どんな権利がついているか(抵当権・地上権など)
- 面積・構造・住所などの物理的な情報
が記録されています。
この登記簿の写しを取得したものが「登記事項証明書(=登記簿謄本)」です。
登記簿の構成:3つの部
登記簿は、大きく3つの区画に分かれています。
| 区分 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 表題部 | 不動産の物理的情報 | 所在、地目、面積、構造、床面積など |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する記録 | 所有者、取得原因、持分割合など |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利 | 抵当権、賃借権、地役権などの記録 |
第2章:登記簿でわかること7選(実務で必須のポイント)
① 現在の所有者と持分割合
- 「甲区」の最新記載に注目
- 複数人で共有している場合、持分も明記されている
→ 例)2分の1ずつ、3分の1など
✅ こんなときに重要:
- 売買相手が真の所有者か確認
- 相続登記が未了なら所有者不明土地の可能性
② 所有権の移転履歴
- 「○年○月○日 所有権移転」など、過去の登記も残る
- 原因も記載:売買・相続・贈与・競売など
✅ こんなときに重要:
- 相続回数が多い物件(管理が不十分な可能性あり)
- 競売履歴のある物件(金融的なリスクの有無)
③ 抵当権や根抵当権の有無
- 「乙区」に抵当権が設定されていれば、債務の担保にされている
- 債権額、債務者、債権者(銀行など)も記載
✅ こんなときに重要:
- 購入予定物件に残債があるか?
- ローン完済後も抹消登記がされていないケースも多い
④ 地目・地積などの土地情報
- 「表題部」にて、宅地・田・畑・雑種地などがわかる
- 面積は「登記地積」。必ずしも現地と一致するわけではない
✅ 注意点:
→ 地目「畑」は農地法の制限対象。売買に農業委員会の許可が必要
⑤ 建物の構造・用途・床面積
- 木造・鉄筋コンクリート造などの構造、階数
- 用途:居宅、事務所、店舗など
✅ こんなときに重要:
- 賃貸併用住宅や店舗付き住宅を見分ける
- 建築確認済証との整合性確認にも使う
⑥ 所在・地番(住居表示とは異なる)
- 表題部の「所在」「地番」は登記上の住所
- 実際の住所(○○市△丁目×番地)とは異なることが多い
✅ 調査時の注意点:
→ 住居表示変更された地域では、地番から住居表示を役所で照会する必要あり
⑦ 地役権・賃借権など他人の権利の有無
- 「乙区」に記載。たとえば、
- 地役権:他人の土地を通行できる権利
- 賃借権:第三者が借りている情報(ただし登記されていないことも)
✅ 要注意:
→ 賃借権が登記されていないと、入居者の有無がわからない=現況確認が必須
第3章:登記簿では「わからないこと」もある!6つの盲点
登記簿は公的資料ですが、「完全な情報源」ではありません。
見落としがちな“登記簿の限界”を把握しておきましょう。
① 現在の地価・市場価格はわからない
- 登記簿に価格は記載されていない
- 「売買による所有権移転」はあるが金額は不明
→ 相場や実勢価格はレインズ・土地総合情報システム等で確認を
② 現況の面積・形状とは一致しないことも
- 登記面積(地積)は古い測量基準のことも多く、誤差あり
- 境界確定や実測は別途必要
→ 売買契約時には「実測精算」があるか確認を
③ 境界線・越境状態は登記されない
- ブロック塀や樹木の越境、境界未確定状態は登記には反映されない
→ 境界確認書や現地調査が必要不可欠
④ 建物のリフォーム・増築歴はわからない
- 表題部の構造は“新築当初”の内容が記載されていることが多い
→ 現況と一致しないケースあり。建築確認通知書などで再確認
⑤ 所有者の連絡先や死亡情報はわからない
- 名前・住所は記載されるが、電話番号などはなし
- 所有者が亡くなっていても、相続登記未了だと登記は更新されない
→ 所有者不明土地問題の一因にも
⑥ 現在の使用状況・入居状況は登記されない
- 空家か賃貸中か、誰が住んでいるかは不明
- 賃借権の登記がなければ調査ではわからない
→ 現地確認・不動産業者へのヒアリングが必要
第4章:登記簿謄本の取得方法と注意点
① 法務局で取得する(窓口・郵送・オンライン)
- 【窓口】最寄りの登記所(法務局)で申請
- 【郵送】必要書類を送付
- 【オンライン】登記情報提供サービス(法務省)
✔ 料金目安
- 登記事項証明書:1通600円(窓口)
- オンライン提供情報:PDF出力 1通335円
② 必要な情報:地番(住所とは異なる)
- 地番が必要(住居表示ではNGなケースあり)
- 固定資産税通知書などで確認できる場合も
③ 失敗例:間違った地番で取得してしまった
→ 地番と住居表示のズレで“隣の土地の登記簿”を取ってしまう人も
→ 地番の確認は、役所の資産税課や地図資料で行うと確実
第5章:実践例で理解!登記簿からこんなことがわかる
実例①:所有者が複数人=相続未登記の可能性
→ 「昭和56年 所有権移転・相続」で止まっている場合
→ 相続登記未了で、売却や担保設定に支障が出る
実例②:表面上は更地→でも抵当権が残っていた!
→ 「乙区」に旧所有者名義で抵当権登記が残存
→ 抹消登記されていないと、金融機関や買主に不信感を持たれる
実例③:地目が「畑」=農地法の許可が必要
→ 売買や宅地転用に行政の許可が必要
→ 「地目変更登記」がされていない土地は要注意
最後に:登記簿は出発点。現地と併せてこそ意味がある
登記簿謄本は、不動産を「公的に確認する」ための出発点です。
しかし、それだけで「物件のすべて」が分かるわけではありません。
大切なのは、
✅ 登記簿で得られる情報を正しく読み取る
✅ 限界を知った上で、現地・役所・周辺住民からの情報も合わせる
✅ 書類に現れない「現況」を軽視しない
という三点です。
✅ チェックリスト:登記簿で確認すべきポイント
| チェック項目 | チェック済み |
|---|---|
| 所有者の氏名・持分割合 | □ |
| 所有権移転の原因と履歴 | □ |
| 抵当権や根抵当権の有無 | □ |
| 地目と面積の確認 | □ |
| 建物の構造・床面積の整合性 | □ |
| 地役権・賃借権の記載有無 | □ |
| 表示住所と地番の違いに注意 | □ |
まとめ:登記簿謄本は「読む力」が鍵を握る
登記簿はただの「紙の情報」に見えますが、
それをどう読み解くかによって、不動産に対する見方が大きく変わります。
トラブルを避けるも、価値を見極めるも、「登記簿の読み方」次第。
専門家に頼らずとも、自分で読めるようになることが、不動産リテラシーの第一歩です。

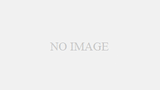
コメント