不動産の購入や賃貸、投資の現場では、物件の「写真」だけで判断してしまう人が意外と多くいます。しかし、写真には写らない、あるいは「写していない」現地の重要情報こそ、あとから問題になることが少なくありません。
この記事では、実際に現地を訪れることでしかわからない要素と、写真だけでは見抜けない注意点について詳しく解説します。不動産選びで後悔しないために、あなたの“目”と“足”で確認すべきポイントを知っておきましょう。
第1章 写真と現地のギャップをなめてはいけない
1-1 加工・選別される「不動産写真」
不動産の掲載写真は、基本的に物件の“良いところ”しか写していません。明るく見せるために時間帯を選んだり、広く見せるために広角レンズを使用することも多くあります。ときには、都合の悪い部分(隣の空き地やゴミ置き場、古い建物など)を意図的に写していないケースも。
1-2 現地に行くとわかる「写真の外」
写真では綺麗な部屋でも、実際には周囲が騒がしい、日当たりが悪い、変なにおいがする、などの問題があることもあります。視覚だけでなく、聴覚・嗅覚・感覚でしか確認できない情報は非常に多いのです。
第2章 写真では絶対にわからない8つのポイント
2-1 騒音と振動
写真では静かに見える通りでも、実際には交通量が多く、車やバイクの音が絶え間ないことも。近隣に学校や公園、工場、線路がある場合は時間帯によって騒音レベルが変わります。また、地盤や建物の構造によっては、振動も感じられるかもしれません。
2-2 匂い・空気感
飲食店や工場、ゴミ置き場の近くでは、特有の匂いが漂っていることがあります。また、川沿いや湿地帯では湿気の多さを感じたり、建物自体にカビ臭さを感じることも。
2-3 日当たりと室内の明るさ
南向きという情報だけでは、十分な日当たりがあるとは限りません。隣接する建物の影、樹木、ベランダの深さなどが影響し、思ったほど明るくないことも。特に冬場や曇天時の確認が有効です。
2-4 周辺環境と雰囲気
写真には写らない、地域全体の雰囲気や治安の良し悪しも現地でしか分かりません。放置自転車が多い、路上駐車が目立つ、ゴミが散乱している、地域住民の態度など、生活者目線での“空気”を感じ取ることが重要です。
2-5 共用部・管理状態
写真では室内だけが美しく写されていますが、エントランスや階段、ポスト回り、駐輪場などの共用部が荒れていると、住人の質や管理状況に不安が残ります。掲示物の乱雑さや汚れ、設備の劣化などにも注目を。
2-6 建物の傾き・劣化・異常
写真では分かりにくい建物の細部、たとえば外壁のひび、雨樋の破損、排水のにおい、建物のわずかな傾きなどは、実際に見ることでしか確認できません。スマートフォンの水平器などで簡易チェックも可能です。
2-7 近隣との距離感や関係性
隣家との窓の位置や距離、ベランダの位置関係、塀越しの目線の高さなど、プライバシーや騒音の影響を受けやすい関係性が見えてきます。また、近隣住人の様子(庭の手入れ、あいさつの有無)も要チェックです。
2-8 災害リスクとハザード情報
ハザードマップの情報と現地の地形・環境を照合することで、実際のリスクを体感できます。例えば「浸水想定区域」とされていても現地は傾斜地で意外と安全そう…逆にまったく気づかずに低地だった、ということも。
第3章 現地調査で見るべき時間帯と天候
- 【朝】…通勤通学の交通量、日当たりの角度、騒音チェックに適
- 【昼】…全体の明るさ、建物の劣化、周辺住民の活動の様子
- 【夕方〜夜】…治安や街灯、周辺施設の営業音、夜間の騒音
- 【雨の日】…排水の様子、水はけ、ぬかるみ、においの発生などが顕著になる
第4章 現地調査を補完するチェックリスト
| 確認項目 | 内容例 |
|---|---|
| 騒音 | 車・電車・人の声・工場・店舗など |
| 匂い | 下水・飲食店・ゴミ・カビ・ペット臭など |
| 日当たり・風通し | 時間帯による変化、周辺の遮蔽物など |
| 管理状況 | 掲示板、共用廊下、駐輪場の整理、清掃状況 |
| 近隣の雰囲気 | ゴミの出し方、放置車両、路上喫煙、ペットの扱い |
| 建物の劣化や異常 | 外壁のひび割れ、傾き、排水異常など |
| 災害リスク | ハザードマップ×現地の高低差や水路 |
| プライバシー・距離感 | 隣地との境界、目線、騒音の伝わり方 |
第5章 まとめ:写真と現地は「別物」だと心得る
どれだけ高性能のカメラで撮影された写真でも、それは現地の“断片”でしかありません。写真は「きれいに見せるためのツール」であり、決して物件のすべてを映し出すものではないのです。
現地でしか得られない情報――それは、不動産選びの命運を左右します。
だからこそ、自分の五感を使って物件を見に行き、「ここに住めるか?」「住みたいか?」という感覚を持つことが、不動産選びで後悔しない最大のコツなのです。

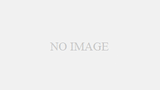
コメント